|
||||||||||
|
||||||||||||
|
大昔の日本の人は、拍手をしていた 大昔の人は、挨拶で拍手(かしわで)もしていたらしい? 中国の歴史書「魏(ぎ)志(し)倭(わ)人(じん)伝(でん)」には、倭(わ)人(じん)(わじん=日本人)は、「偉い 人に会ったときは手を打つ」と記されているそうです。 つまり、握手と同じように、人と会うと拍手を打ったとのこと。 この拍手(かしわで)は「魂振(たまふり)」といわれ、立てる音で神様を招き寄せ、お互いの 魂をふり動かすという神がかりの祝福の方法のようでした。 今にも残る習慣の一つ、参拝に拍手を打つことだそうです。 初詣(はつもうで)、それから七五三、合格祈願するときに柏手(かしわで)するのはそこから 来ているようです。 ちなみに、一般的な拍手の打ち方は、二度礼をして二回パンパンと 拍手最後に一礼します。 七五三の時は、二回礼をして二回拍手してから祈願する、それから 二回拍手して一礼して終わります。 出雲大社だけは、拍手は二回ではなく四回するようです。 余計なことですけど、 葬儀の時の拍手は、玉串を捧げたあとに、二回礼をしてから、拍手 となるのですが、「忍び手」という動作、拍手するように手を打つよ うにして途中で止め、音を出さないようにするのです。 二回して一回礼をしておわります。 この動作は、私が子供の頃「しのびれの作法にしたがって」と、聞 かされていました。 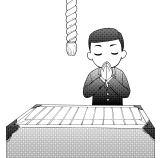 |
|||||||